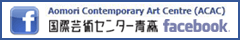地域連携センター 研究員紹介
研究員一覧
| 役職 | 氏名 | 専門分野 | コメント |
| 地域連携 センター長 | 生田 泰亮 | 経営統治論 地域の産業・企業の戦略とマーケティング | 「ものづくり」「手仕事の世界」「地場産品」「伝統的工芸品」「お土産」などをキーワードに、学生と地域について学んでいます。地域の伝統や文化、生活の知恵を後世に継承していくとともに、顧客に喜ばれる商品を生み出す事業をいかにマネジメントするかを模索することが地域に根差した事業にとって重要なことだと考えています。また、その土地に住んできた人々の英知を学び「変わらないものと変わるもの」「変えるべきものと変えてはならないもの」を見極めつつ、工夫、改善、試行錯誤を繰り返すのが手仕事の日々の姿であり、地域の未来をつないでいく事業の条件だと考えています。 |
| 専任研究員 | 後藤 厚子 | 農業経済学 生活経済論 地域研究 (研究キーワード:農業政策、農村社会、地域活性化) | ヒト・モノ・資源の循環という視点から、地域資源の保全・活用による新産業創出と暮らしの場の再構築に向けた実践事例について調査・検討をおこなっています。本県農林水産業の持続的発展と共生社会を支える担い手を育成するためには、〈農業生産〉の効率性を追求するのみならず、〈農村生活〉の中で育まれてきた地域の伝統文化や技術の維持・継承を通じて、〈労働〉と〈消費〉のあり方を見直す機会の創出が不可欠であると考えます。地域住民が当事者として「人と人」「人と地域社会」とのつながりを主体的に考え、多様な活動を展開していく上での一助となるよう、研究教育活動に取り組んでまいります。 |
| 専任研究員 | 松本 京子 | 持続的農村開発論 地域資源管理 気候変動適応策 地域連携教育 | 国内外の農山漁村地域を対象にインタビューやアンケート調査などの手法を用いて持続的な農村開発に関する研究を行っています。行政の手の届かない地域での住民主体による資源管理の持続可能性、少子高齢化の進む地域での定住促進に向けた地域資源を活用した教育の学習効果検証、自然災害や気候変動に対する個々人の意識と行動選択の違いの要因分析、などの地域を取り巻くさまざまな課題解決に向けたテーマに興味を持って調査研究を実施しています。今後は青森県にもフィールドを広げ、地域の力で豊かな暮らしを実現する方法を考え、地域の課題解決と持続可能な農村社会の実現に寄与する研究を進めたいと考えています。 |
| 兼任研究員 | 大森 史博 | 哲学 倫理学 | この研究がおこなう「浅虫てつがく対話」事業は、青森の〝ランドマーク〟のひとつ〝浅虫〟の地に〝子どもから大人まで〟ともに参加できる対話の場所をつくり、対話の可能性を探ろう、というワークショップの試みです。お互いに問いかけ、言葉を交わすことは楽しい。そうして目覚めた探究心や発見の面白さは、小さい子どもでも、大人になってからでも、ともに味わい共有することができます。ふだんは通り過ぎてしまう素朴で大切な問いを、ことあらためてじっくり考える機会となること、地域と大学の相互的な交流の場となり、この世界と人間について学びなおす多様な知の萌芽となることを目指します。 |
| 兼任研究員 | 佐々木 てる | 国際社会学 地域社会論 国籍研究 ねぶた研究 他 | 人は社会とのつながりの中で、人として自分を認識し、生きていると考えることができます。地域社会はまさに、そのつながりの現場であり、そのつながりの要素となるものは、仕事であったり、趣味であったりと様々なものがあります。私はこうしたつながりの核となるものを「文化」ととらえ、青森の「地域文化」を考えていきたいと思います。そしてその文化が地元の周囲の人だけでなく、少しでも世界の人とつながるきっかけになるよう、発信してきたいと思います。 |
| 兼任研究員 | 丹藤 永也 | 英語教育学 応用言語学 | 地域に根ざした英語教育を目指し、青森の児童生徒の英語力並びに英語教員の指導力向上の一助になるよう、研究を推進したいと考えております。研究成果については研究会の開催や論文により、地域の皆様に還元したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 |
| 兼任研究員 | 長岡 朋人 | 解剖学 人類学 | 私は解剖学・人類学の専門家として、15年間南米の遺跡におけるフィールドワークに関わり,アンデス考古史上大きな成果を挙げています。これまでの実績と文理融合の視点に基づいて、遺跡発掘資料の科学分析や文化遺産のデジタル化を武器に、地域の歴史的価値の発見に貢献する研究活動を進めています。 |
| 兼任研究員 | 野坂 真 | 災害社会学 地域社会学 記憶研究 社会調査法 | 災害や少子高齢化など、地域の存続を危うくする危機が各地で起こっています。それに備え、それぞれの地域が持つ共助(助け合い)や縦割り的な領域を超える協働の仕組み、地域を超えた広域連携のあり方や関係人口とのより良い関わり方などがいかに成り立ちうるのか、地域の個性を見つめ直し生かすことで、危機が襲っても立て直せる持続可能な地域社会をつくることを目指しています。これまで、東日本大震災の津波被災地や過疎が進む地域で質的・量的両方の調査法(インタビュー、質問紙調査、ドキュメント分析、参与観察など)を駆使したフィールドワークを行い、地域アーカイブ活動や地域の防災計画の見直し、震災遺族の心の復興過程の記録づくりや大学生を被災地へ案内することによる震災伝承活動などにも携わってきました。地域社会が本来持つ自己治癒力=レジリエンスを高めるお手伝いができるよう地域と連携していきたいです。 |
| 兼任研究員 | 藤沼 司 | 経営管理論 経営学史 経営哲学研究 | こんにち、さまざまなところで「協働」という言葉を見聞きするようになりました。例えば、地域課題の解決には特定の個別経営体(行政、企業、NPO等)だけではなく、多様な利害関係者がそれぞれの専門性を生かしながら協働する必要性があると言われます。問題は「どうすれば効果的な協働が可能か」です。 経営学が「人間協働の学」と言われます。協働は人間の核心的な特質であり、協働をよりトータルに捉えようとする点に、すなわち人間が生きていることの全体性を捉え、よりよく生きるための方途を探る点に、経営学の魅力・可能性があります。その経営学の教えるところは、協働の成立・存続・発展の困難さです。 私はこれまで、経営学における協働の捉え方の特徴や問題性を原理的に検討(経営哲学研究)してきました。さらに研究を進めるため、<いま・ここ>で展開される具体的な協働への参画が重要と考え、近年ではまちづくり協議会や地域包括ケアシステムなどにも関心をもって関わっています。 |
| 兼任研究員 | 三浦 英樹 | 地理学 地形地質学 第四紀学 | 一見ありふれた場所のように見えても「何もない」地域というのは絶対にありません。地域の自然環境とその成り立ち、それらと人々の暮らしとの関係には、必ずかけがえのない特有の個性があります。地球規模の空間スケールと地質学的な時間スケールの視点から地域を探り、考えることは、「何もない」と思っていた地域の中から、今まで見落としてきた、思いがけない価値を再発見することに繋がります。それは、地域への誇りを取り戻すことになり、地域で生産される農林水産物の付加価値を高め、知的な観光旅行を楽しむための素材を提供することになります。このように、地域において、土地と人々の歴史を「環境史・自然史」の形で語り、現在という時代における環境と人間の歴史的位置づけを考え、土地が持つさまざまな個性にもとづいた「ナラティブ(物語)」を付加することを通して、青森県を“知的にブランディング化”することを目指します。 |
| 兼任研究員 | 安田 公治 | 少子高齢化 未婚・晩婚化 農業 教育 | 私はこれまで少子高齢化問題を背景として、未婚・晩婚化の問題や農業の離農、後継者問題の研究に取り組んできました。特に高齢化や少子化による後継者不足はどの分野でも影響が大きく、私は農業者が農業を継続、拡大していく要因についての研究にも現在取り組んでいる所です。 青森市や青森県全体でも農業者の高齢化や離農問題は今後深刻化していくおそれがあり、高齢農家の負担の軽減や農地の担い手を確保していく必要が高まってきています。農業を継続、発展していくためには後継者の確保や育成、外部からの人材の流入の促進も重要となりますが、そのためには地域の内外からの農業従事者が農村地域内で生計を得て、結婚や子育てなども安心して行える環境を整備していくことが重要になると考えられます。 今後の研究ではこれまでの研究経験を活かし、農村地域での生活環境の維持、改善が後継者確保や離農の抑制に与える影響の研究に取り組んでいくつもりです。 |
| 兼任研究員 | 渡部 鮎美 | 民俗学 地域研究(日本・韓国) | 日本や韓国の農山漁村を対象に地域の自然・文化資源の利活用について研究をしてきました。 これまでの研究では農業を支えるパートタイマー、東北地方の出稼ぎ、新潟県の高齢者福祉と二地域居住、各地の食文化、地域の文化を生かした町づくりなどがテーマでした。 近年は漁業と環境保全に関する研究も進めています。現場の問題を聞き取りや実測、統計資料等の活用によって詳細に分析し、地域の方法で地域の課題の解決をすることを目指します。国に対する必要な支援を求める際のアシストなどもできればと考えています。 |
| 事務長 | 鹿内 一徳 |