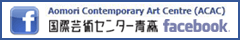模擬講義(出張講義)タイトル・概要一覧
※青森公立大学 入試サイトを開設しました。入試に関する最新情報は必ず下記リンクからご覧ください。
青森公立大学 入試サイト

経営学科
| 教員名 | 職名 | 講義タイトル(例)・概要 |
| 金子 輝雄 | 教授 | 企業経営における会計の役割について 企業における諸活動を記録し損益を計算する会計は、経営の基本ですが、会計数値を活用して、より効率的・安定的なマネジメントが可能になります。 財務諸表による収益性・効率性・安全性の分析、利益計画としての損益分岐点分析、PDCAサイクルとコスト・マネジメント等を中心に、加えて、SDGsを念頭にESD(環境・社会・ガバナンス)経営にむけた会計の有効性について話したいと思います。 |
| 紫関 正博 | 教授 | 「ビジネスの言語」会計の役割と特徴 会計は「ビジネスの言語」と呼ばれ、経済活動に関わる人々がビジネスを行う際に必要なコミュニケーションのための道具となっています。会計は「用語」と「金額」を用いて、企業をはじめとする経済組織の過去・現在の経済活動や経済事象の他に、将来を予測して見積った事柄(将来事象)を会計文書に表わすことにより、会計情報を利用する人々に役立つ情報を伝達することが求められています。 会計にはどのような役割があるのでしょうか。本講義ではその役割を紹介し、現代の会計の特徴についても説明します。 |
| 長谷川 美千留 | 教授 | 財務諸表分析を学ぶ 財務諸表分析は、経営分析、財務分析とも呼ばれる。企業が制度のもと開示する財務諸表に対し、おもに4つの観点(安全性・収益性・生産性・成長性)から検討をする分野である。簿記の知識やが会計学の知識があまりなくとも、基本的な財務指標をいくつか用いて、財務諸表分析をすることは可能である。身近な企業や関心のある企業を分析してみることで、当該企業の経済的実態を把握できる。そこに企業広告のイメージとは異なる、企業の真の姿を見出すかもしれない。 |
| 藤沼 司 | 教授 | 経営学とは何か―私たちが「協働の経営学」を学ぶ意義― 私たちの生活が様々な組織に支えられており、現代社会が「組織社会」と言われます。「組織」には、企業のような営利組織、行政、病院、学校、ボランティア、家庭のような非営利組織があります。様々な組織をどのように経営するかが私たちには重要な問題です。またこんにちでは、社会や地域の課題解決には個別組織だけでなく、多様な専門性をもった利害関係者が協働する必要があります。こうしたクロスセクター協働の経営に、経営学が重要な示唆を与えるので、その要点をお話します。 |
| 池田 享誉 | 准教授 | 青森公立大学経営学科で学ぶ意義 ―社会で活躍するために― 1 大学へ行く意味 何のために大学へ行くのか。 2 経営学科で学ぶこと 2-1 「市場と戦略」 2-2 「人間と協働」 2-3 「会計と財務」 3 経営学科で学ぶことにより得られる力―就職との関連― 実際の就職内定実績を示しつつ、経営学科で得られる力の社会での生かし方12種類について説明する。 |
| 中川 宗人 | 准教授 | 「就社」からみる日本の雇用システムと就職活動の歴史 世界のなかでも日本に独特とされる慣行として、毎年4月に全国の生徒・学生が一斉に就職する「新規学卒一括採用制度」があります。この制度・慣行は日本の大企業における「日本型雇用システム」と日本の学校教育とが結びついて形成されてきたもので、若者が職業を意識して働くことよりも(就職)、会社のメンバーとなることを意識して働く「就社」社会を作り上げている要因とされています。この講義では、戦後日本の採用制度・就職活動の歴史の検討を通じて、「就社」社会の課題を考察します。 |
| 行本 雅 | 准教授 | エシカル消費 ―消費を通じて人や社会・環境について考える 近年では、企業の社会的責任や社会的な価値への貢献が強く求められるようになってきています。こうしたなかでマーケティングにおいては、品質や価格だけでなく、社会的責任や社会的な価値に配慮した製品やサービスを提供しようという取り組みがなされています。 本講義では、フェアトレード・ラベルや海のエコラベルといった、消費者の選択によって社会的な価値の実現を目指そうという取り組みについて紹介します。 |
| 王 聖書 | 講師 | 管理会計って何 この授業では、「管理会計」という分野について話します。管理会計とは、企業がよりよい経営判断を行うために使う会計のことです。たとえば、「どの商品をどのくらい作れば利益が出るのか」「経費をどこで削減できるのか」「社員のやる気をどう引き出すか」といった、会社の中の意思決定やマネジメントに役立つ情報を提供します。近年では、環境への配慮やSDGsのような社会的課題も重視されており、持続可能な経営を支える「サステナビリティ管理会計」についても紹介します。 |
| 長谷川 直樹 | 講師 | リーダーシップについて学ぶ 青森公立大学経営学科の中で一つのキーワード(ディプロマポリシー2に記載されている)として「協働」がある。この「協働」を確立するためにどのようなリーダーシップが必要になるのか。現代社会では、よくリーダーシップが不足していると言われることがあります。そもそもリーダーシップとは何か。どのようなリーダーシップが存在するのか。なぜリーダーシップが重要なのか。これらについて説明します。 |
経済学科
| 教員名 | 職名 | 講義タイトル(例)・概要 |
| 青山 直人 | 教授 | 市場の役割と政府の役割 皆さんは社会の授業で、市場経済のしくみと価格について勉強したことがあると思います。それでは、市場取引におけるメリットについてはどうでしょうか。講義では、市場メカニズムと市場取引のメリットについてお話しします。 一方で、市場メカニズムがうまく機能しないときもあります(市場の失敗)。市場が失敗している場合はどうすればよいのでしょうか。講義では、市場の失敗例として、環境問題を取り上げます。環境問題発生の原因とメカニズムについて学び、政府の役割を考えてみましょう。皆さんが社会の授業で勉強したことを、大学ではどのように勉強しているのか体験してほしいと思います。 |
| 大矢 奈美 | 教授 | 社会保障制度からみる少子化対策 少子化問題の解決は喫緊の課題です。少子化が生じた背景には産業構造の変化や女性の労働市場への参加、一方で依然として残る家庭内役割分業など考えられ、様々な方面からの対応が必要とされています。中でも注目されているのが児童手当などを含む社会保障制度です。しかし社会保障制度は、本来の財源である社会保険料と税金で賄いきれず、公債発行に頼る状況です。この講義では経済の側面から社会保障制度の規模と役割を概観し、少子化対策として何が可能なのかを考える材料を提供します。 |
| 樺 克裕 | 教授 | まちづくりと地方財政 21世紀に入り、60年代、70年代に建築した役所、学校、橋梁や水道等の社会資本の老朽化が進行している。高齢化が進み年金、医療等の社会保障給付費が年々増加する中で、社会資本を再整備するための費用も年々増加しています。 一方で、借金である日本の長期債務残高は1,000兆円を超え、社会資本を再整備する予算にも限りがあります。 そのような状況の中で、どのようにして社会資本を再整備し、まちづくりを進めていくべきかについて、研究内容と実務経験等を踏まえて説明します。 |
| 木立 力 | 特別 教授 | 年収の壁と学生や女性の働き方 「103万円の壁」という言葉がありますが、年収が103万円を超えると所得税がかかるので年収をそれ以下に抑える壁になるという意味です。2024年の政治テーマの1つになったことは知っていますか。2025年度税制改正では、壁は引き上げられ160万円まで所得税がかからなくなりました。この「壁」を手掛かりに所得税のしくみ、日本の財政の現状、労働力不足の現状を解説します。 |
| 橋本 悟 | 教授 | 2050年のカーボンニュートラルに向けて 温暖化や激甚化する災害等に対応するため、我が国は2050年に社会・経済活動におけるCO2の排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を宣言した。 CO2の排出をなくすためにエネルギー業界では、水素・アンモニア・合成メタンの技術開発が行われている。しかし、水素・アンモニアは燃焼時にCO2を排出しないがサプライチェーンを構築する必要があり、一方で、合成メタンは、サプライチェーンはあるが製造過程の技術に課題がある。 本講義では、このエネルギー業界の技術開発の現状と将来性について紹介する。 |
| 工藤 恭嗣 | 准教授 | 取引と競争-(市場における)交換を通じた知識や知恵の社会的共有 お店で商品やサービスを受け取るとき、私たちは単にお金とモノを交換しているのではなく、その背後にある知識や技術も共有しています。農産物、工芸品、スマートフォンなど、商品やサービスは、労働や経験、試行錯誤の積み重ねによって生まれた「知識や知恵の結晶」です。市場は、知識や知恵が形になり、消費者へ届けられる場となっています。この講義では、生産者間の公正で自由な競争や消費者の適正な選択を支える規制にも触れながら、取引と競争を通じて知識や知恵が社会に共有されること、そして、競争について、勝敗を決める装置ではなく、社会を豊かにする営みとなっていることを学び、競争の意義について考える機会を提供します。 |
| 七宮 圭 | 准教授 | 統計データでみる経済 コンピュータやインターネットの発展にともない、統計学を用いたデータ分析が様々な分野において盛んに行われています。経済学の分野においても、理論の正当性を検証するために、観測されたデータを理論に当てはめた分析や経済の予測などが行われています。本講義では「統計データからみる経済」として、経済学の基本的な考え方と経済学における統計の役割について解説を行います。 |
| 山本 俊 | 准教授 | 金融を通じて私たちの暮らしを充実させよう! みなさんは「金融」にどんなイメージをお持ちですか?「難しそう」とか、「私には関係ない」と思う方もいるかもしれません。しかし、金融は皆さんのライフサイクルの中で、密接にかかわっており、金融の仕組みや考え方を知っていれば、皆さんの暮らしはもっと充実するかもしれません。 この講義では、皆さんの暮らしを充実させるという目標を掲げ、ときにはグループワークやマジックなども交えながら、金融の仕組みや制度、考え方を学修します。お気軽にご依頼ください。 |
| 黄 年宏 | 講師 | 3つの物語で学ぶ経済学の役割とその重要性 1. 中絶と望まれない子ども(ロー対ウェイド事件・教育経済学) Donohue & Levitt (2001, 2019):州別に犯罪率と出生コホートを追跡し、「中絶率の高い州ほど、その子ども世代が成人する1990年代に犯罪減少が大きい」と報告。 2. なぜ核兵器を保有するのか?(米ソ冷戦・ゲーム理論) 核兵器保有は相互抑止による均衡達成を目的とする。もし武器を増強せず、平和的な協議を行えば、よりよい状況は実現するのではないか? 3. 美しさは重要か?(美貌格差・労働経済学) Hamermesh(2011):上位15%の美男美女は、下位15%の平均的な外見の人々に比べ、約15%高い収入を得ている。 |
地域みらい学科
| 教員名 | 職名 | 講義タイトル(例)・概要 |
| 足達 健夫 | 教授 | まち歩きからユニバーサルデザインへ ~見て歩いて、広がる世界 見なれた街も、その気になって観察するとさまざまな知識の世界へつながっています。今回は、ふだんなら気にもとめないありふれた「タウンサイン」に着目します。文字を使わずに道ゆく人びとにまちの情報を伝えるために、だれにとってもわかりやすくデザインされるタウンサイン。まち歩きから始まり「ユニバーサルデザイン」と呼ばれるデザイン思想まで続く道のりを、途中いろいろな学問の分野に寄り道しながらたどります。 |
| 佐々木 てる | 教授 | 伝統と祭礼研究:「青森ねぶた祭」を事例として 青森市の夏の風物詩である「青森ねぶた祭」。この全国的にも有名な祭はどのような経緯で成立し、そして継承されているのか。また他の日本の祭である、灯篭文化系の祭や、京都の祇園祭との関係はあるのか。こういった問いから、なぜ祭礼文化が伝統として継承されるのかを考察していく。特に分析の視点として、長く培われてきた「日常文化」をキー概念とし、人々のライフストーリーから分析していくことにする。 |
| 長岡 朋人 | 教授 | 海外におけるフィールドワーク 私は人類学の専門家として、15年間南米におけるフィールドワークに関わり,アンデス考古史上大きな成果を挙げた。本講義では,これまでの研究の実績や青森公立大学におけるゼミ活動の紹介を通して,フィールドワークの面白さ,文理融合の研究の試み,そして大学で学びを深める魅力について語りたい。 |
| 三浦 英樹 | 教授 | 地域の自然史の読み方・考え方・楽しみ方 毎日、なにげなく見ている身近な風景。風景は、地形、植物、天候などの自然に加えて、それらを利用してきた人々の歴史や文化とも深く結びついています。本講義では、風景に記録された地域の自然の生い立ちを第四紀という新しい地質時代までさかのぼって考え、どのような変動を経て現在に至ってきたのかを読み解きます。わたしたちが、自然史を読む楽しさを知り、その意味を理解して、地域への愛着を深めることは、地球や地域の環境保護、地域資源の学術的価値の創出、自然災害や公害の軽減の基礎ともなり、地域の魅力を再発見することに繋がるに違いありません。 |
| 生田 泰亮 | 准教授 | 経営経済学から学ぶイノベーション −イノベーティブな発想を身につけよう− 「便利」や「当たり前」だと実感することの多くは、実は、ちょっと前の「不便」や「不満」から生まれてきます。イノベーションは、経済、産業、企業を大きく動かし、歴史や文化、人々の生活を変えてきました。本講義では、イノベーションによって「何がどう変わるのか?」を考察し、イノベーションにとって「どのような発想や思考が重要なのか?」を問います。企業や人々がどのように新たな技術や商品、サービスを生み出してきたのかを過去の歴史、現在の日常生活の中から学びます。 |
| 野坂 真 | 准教授 | 東日本大震災から学び、今後の災害に地域でそなえる 日本各地で災害が頻発し、また大災害の発生が想定されている。例えば、国の設置した検討会がまとめた、日本海溝・千島海溝沿い地震に関する報告書では、北海道・青森県・岩手県の沿岸部を中心に最大20m以上の津波の来襲が切迫していると言われている。今後起こりうる災害にそなえ、過去に起こった災害、特に東日本大震災について、なぜ戦後最大と呼ばれる被害が生じたのか、その後の復興過程で何が起こってきたのか(今も起こっているのか)、今後同じ被害や復興上の問題を繰り返さないようにするにはどうすればかいいのか、を学ぶ。 |
| 渡部 鮎美 | 准教授 | 漁業と環境問題 海洋汚染、気候変動による水温の上昇など、海の環境問題は年々、深刻化しています。環境の変化によって、海で獲れる魚の種類や量も変わり、国内では水産資源保護のための漁獲制限も行われているため、漁師さんたちの生活へも大きな影響があります。本講義では、漁師さんたちが海の環境問題をどのようにとらえ、漁業をしてきたのかを紹介し、地域の人びとと環境問題に取り組む上で大切なことについて考えます。 |
| 安田 公治 | 講師 | なぜ結婚や子どもの数が減っているのか・経済学の考え方 日本では結婚をする人や子どもの数が減るようになり、それが大きな社会問題となっています。また日本では子どもの数が減った事は結婚をする人が減った事と強く関係していると言われています。結婚をしない人には、大きく分けて生活が便利になり結婚をする必要がないと感じている人や結婚をしたいが収入が安定しないなどの理由で結婚できない人などが考えられます。経済学では金融や財政などの問題も扱いますが、人が結婚や子どもの数をどのように決定するかについても経済学的に考えることが出来ます。この講義ではなぜ結婚する人や子どもが減ったのかについて、またそれを経済学の基本的な考え方についても触れながら学んでいきます。 |
教養科目
| 教員名 | 職名 | 講義タイトル(例)・概要 |
| 小林 直樹 | 教授 | 物語で「法律(法)」を学ぶ 「法律(法)」というと、難しい言葉が並び、堅苦しいイメージがあると思います。しかし、私たちの社会は「法律(法)」によって成立し、しかも、私たちの社会が抱える問題を解決する便利な道具という側面があります。 堅苦しいイメージを抱かせる「法律(法)」ですが、私たちが幼いときに見聞きした物語(昔話)を通じて、「法律(法)」の考え方を知り、それを実際に活用し、理解を深め、一緒に問題を解決してみたいと思います。 |
| 鈴木 郁生 | 教授 | 心理学への招待 心理学は、人の心を科学的に研究する学問です。その対象は、五感の働きや記憶の仕組み、注意のシステム、そして社会的行動や個性の形成など多岐にわたります。これまでの心理学研究から、人間の心の意外な働きが分かってきました。そこで、この講義では、基礎心理学における研究を通して、心理学の世界をご紹介しようと思います。学問としての心理学の基礎を知り、人間とその心理について深く考えてみましょう。 |
| 大森 史博 | 准教授 | 哲学をするってどういうことだろう? 「哲学」は、どこにでもあるけれど、どこにもないという不思議な学問です。高校までの授業のなかに「哲学」という科目はないのですが、みなさんが学んでいるどんな科目の背景にも「哲学」があります。それでは「哲学」とは何でしょうか?この謎を一緒に考えてみましょう。その手がかりとして、はじめに注目するのは「言葉」です。講義では、みなさんとの探究的対話をとおして「哲学」への接近をこころみます。 |
| 下村 育世 | 准教授 | 暦から文化を知る 恵方巻や初詣といった年中行事、仏滅・友引の六曜を気にし、還暦を祝うといった風習は、民俗化した旧暦文化と言えます。現代に残るこうした「不思議」に見える風習の背景を探ってみると、江戸時代の太陰太陽暦(旧暦)にルーツがあることを発見することになるでしょう。時間は文化的にいかようにも区切ることができますので、それを表象する暦(カレンダー)は優れて文化的な産物です。現在使われている太陽暦(新暦)と旧暦は何が違うのでしょうか。明治改暦で日本はどういった時間の区切り方を採用したのか改めて考えます。 |
| 西村 吉弘 | 准教授 | 学校を中心とした地域づくりや交流を考える 学校の外に目を向けてみる‐学校と地域の連携・協働を踏まえて 現在、学校と地域が連携・協働活動をすることを通して、学校教育の充実や周辺地域の活性化などに向けて、様々な実践が展開されています。例えば、社会科(地歴公民)や総合的な探究の時間の機会を使いながら学ぶことで、高校生として地域にどのような貢献や提案ができるのか考えてみましょう。 これらの学びが、ひいては地域づくりや地域住民同士の交流、学校を含む地域全体の活性化、そして自己実現へと繋がっていきます。その担い手となるよう、一歩踏み出してみましょう。 |
アカデミック・コモン・ベーシックス
| 教員名 | 職名 | 講義タイトル(例)・概要 |
| 香取 真理 | 教授 | ことばと文化 私たちが毎日、何気なく使っている「ことば」とは何か、よく耳にする「文化」とはどういったことなのだろうか、ということを考えながら、ことばと文化の密接な関係を学生なりに理解してもらう。 また、言葉と脳の関係や、バイリンガルと認知の関係などを通し、母国語以外の言語を学ぶ目的や文化資本としての価値などについて興味を促す。 |
| 丹藤 永也 | 教授 | 英語によるパラグラフ・ライティングの基礎 パラグラフは文章構成の基本単位で、1つのパラグラフがひとまとまりの意味を持ちます。パラグラフの特徴は、主題に対する一貫性のある論理の展開です。内容は書き手の意図がうまく伝わるように構成され、かつ読み手にわかりやすくなければなりません。ですから、パラグラフ・ライティングは、論理的思考力に加え、書くことを通じたコミュニケーション能力の育成にも有効な手段であると言えます。本講義では、パラグラフ・ライティングの基礎について学んでいきたいと思います。 |
| 深田 秀実 | 教授 | 社会情報論入門(イントロダクション) 社会情報論とは,現在の社会から新しい社会への変動を,情報化を進展させるもの(例えば新しいメディア,新しいデジタル技術等) との関連で 捉えて議論する学問分野である. 近年,新たなデジタル技術が開発され,それに伴って生成AIの利活用が始まっている.将来,AIが本格的に利用される「超スマート社会」は,人間を幸福にするのか,皆さんと考えてみたい. (1回の講義:80分~90分程度) |
| 江連 敏和 | 准教授 | はじめてのビジネス英語 英語は普段の生活で使いません。なぜ勉強するのですか?―そう思う方もいるかもしれません。ビジネス英語の学習は、単語や文法、スタイルを学ぶだけではありません。本講義では具体的な場面、(例えば、「必要な情報を求める」「商品やサービスに不満がある」)を想定して会話や文書作成のワークショップを行います。ビジネス英語は、人々が目的を円滑に達成するための有用な行動指針です。学習を通して社会のルールを学んでいきましょう。 |
| エシアナ・べネス | 講師 | Knowledge of Language, and Ability We will look briefly into the purposes of second language acquisition. Following this, we will discuss the differences between “knowledge of language” and “language ability”, the importance and value of both, or one over the other, and finally, look into preferences and their implications in our lives and society. (質問等は日本語でも大丈夫です) |
| 成田 芙美 | 講師 | 労働とは何か ―19世紀のイギリスの人たちと一緒に考える 産業革命を経た19世紀のイギリスでは、人々の働き方に変化があり、労働のあり方が注目されるようになりました。そのなかで、人間にとって労働とは何か、どのように働くことがよいのかを考え、主張した人たちがいました。ヴィクトリア時代の歴史、文化について学びながら、当時の人たちと一緒に、労働のあり方について考えてみましょう。また、少しだけ、当時の人が書いた英文を読むことにも挑戦してみましょう。 |